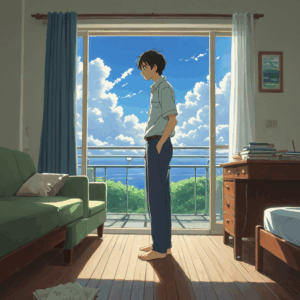OBOG訪問をしようと思っているけど、どうやって探すの?
やり方やマナーがわからなくて、恥をかかないか心配
この記事では、こんな悩みを解消します!!
就職活動の情報収集手段として、昔から活用されているのが OG・OB訪問。
しかし、OBOG訪問について、特に就活始めだと何をすればいいのかよくわからない、という声を多く聞きます。
OBOG訪問は就活において、実は内定にも関わるとても大事なイベントとなります。
就活を有利に進めるためにも、しっかりとOBOG訪問の全体を理解して、「評価される就活生」になりましょう。
この記事を読むと、OB・OGの探し方から当日のマナー、内定への活かし方までの全体がまるっとわかります!
STURENT利用の先輩内定者やリアルOBOGからの成功体験・失敗談も交えるので、ぜひ参考にしてくださいね!
OBOG訪問とは?
OG・OB訪問とは、大学生が入社希望先の先輩社員を訪問し、就職活動やキャリア形成に役立つ情報を得る活動のことです。
会社説明会や求人票では分からない、リアルな職場環境や先輩のキャリアの歩みを直接聞けるので、大変貴重な機会となります。
誰に会うの?
基本的には同じ大学を卒業した先輩にお願いするケースが多いです。
大学のキャリアセンターで紹介を受けたり、ゼミや部活のOBネットワークを活用したりするのが一般的な方法です。
ただ近年は、SNSや就活専用マッチングサービスを通じて、同じ大学卒でない、初対面の社会人にアポイントを取ることも当たり前になってきました。
会える相手は新入社員から管理職クラスまで幅広く、誰に会うかで得られる情報も変わります。例えば若手社員なら「入社直後のリアルな生活」について、管理職なら「業界全体の動きや会社の将来性」について話を聞くことができます。
どんな話を聞けるのか
訪問時に聞ける内容は多岐にわたります。
代表的なのは、日々の仕事内容、やりがいや大変さ、働き方のスタイル、1日のスケジュール、社内の雰囲気など。
さらに「なぜその会社に入ったのか」「就活時にどんな軸で企業を選んだのか」といったキャリア選択のプロセスも参考になりますね。
また、会社説明会ではなかなか触れられない裏話や、失敗談・後悔談も教えてもらえることがあります。
こうした率直な情報は、ミスマッチを防ぎ「入社後に後悔しない選択」をするうえで非常に役立ちます。
ここだけの話ですが特に「ネガティブな話」も意識して聞くようにしましょう。
というのも、企業が公式としてに出している情報というのは、「ポジティブより」な内容が多く、なかなかネガティブな面を知ることは難しいからです。
OB OG訪問のメリットって?
実際に働いている社員さんにお話を聞ける貴重な機会であるのはもちろん、OBOG訪問にはたくさんのメリットがありっます。
企業のリアルな情報を得られる
就活サイトに書いてある事業内容や採用ページの雰囲気だけでは、実際の働き方や社内文化はイメージしにくいものです。(都合のいいことを言いがちなのと、抽象的すぎてわからないことも)
OBOG訪問では、実際に働いている先輩から日常業務の流れや社内の雰囲気、働き方の実情を聞くことができます。
これにより具体的な仕事の流れや、人間関係の特徴が見えてきて、会社に対する解像度があがります。
キャリア形成の参考にする
学生時代にやりたいことを決めるのはなかなか決めることが難しいものです。それはそもそも、「何が選択肢にあるのか」わからないから。
社会で活躍している人の歩みを知ることで、自分のキャリアプランを描くヒントになります。
志望動機や自己PRに活かせる
企業研究の深さはエントリーシートや面接での回答の質に直結します。OG・OB訪問で聞いた具体的なエピソードは、説得力のある志望動機に間違いなく繋がります。
「実際に社員の方から伺った話を聞いて、自分もこの環境で挑戦したいと感じた」といった形で語れると、単なるネット調べの情報との差別化が可能になりますし、志望度の高さを伝えることも可能です。
OB OG訪問はいつから始めるのがベスト?
大学3年の夏から秋頃が一般的
結論から言えば、大学3年の夏以降が目安です。
サマーインターンが終わった頃から、就活に本腰を入れ始める学生が増え、同時に「実際に働いている先輩に話を聞きたい」と思う時期でもあります。
少し就活慣れをしてきて、かつ行きたい業界・企業がぼんやりと定まってきたこの頃にOBOG訪問をしてさらに理解を深めるというイメージです。
早めに動きたい場合は大学2年の冬〜3年生の春からでも
ただし、早めに動きたい人は 大学2年の冬〜3年春から始めるのもおすすめ。
まだ就活を意識していない時期に動くと、先輩からも「熱心だね」とポジティブに受け取られるケースが多いです。
人気なOBOGさんだと、他の就活生からの依頼も殺到してしまい、なかなか繋がれなくなることも。
やる気のある人は早めに、よさそうな人と繋がっておきましょう!
※注意※志望度の高い企業の対しては、焦って訪問しない
「あまりよくわからないけど、早めに話を聞きたいから、準備できていないけどOBOG訪問してみよう」というのは危険な場合があります。
もちろん「就活始めたばかりの人でも大丈夫」 「就活全般の相談にのります」と言ってくれる社会人だったらいいのですが、そうでない場合「あまり志望度高くなさそう」「理解力が低いのでは」と誤解を受けてしまうことも。
後述しますが、OBOG訪問でも実は評価をされていることもあるので、特に志望度の高い企業の社員さんとお話をする際は、時期を急ぎすぎず、ある程度準備ができた段階で依頼をすることをお勧めします。
2. どうやってOB OGを探す?
以前は大学の紹介や、知り合いの先輩など、繋がる手段が限られていましたが、近年OBOGの探し方は多様になってきました。
ここでは知っておくべきメジャーな方法をいくつかご紹介します!
大学のキャリアセンターを活用
オーソドックスなのが、大学のキャリアセンターに登録されているOBOG名簿を使う方法です。
大学によっては学部ごとに細かく整理されており、卒業年度・勤務先・部署まで一覧できるケースもあります。
信頼性が高く、紹介を通じて訪問依頼できるため、初めての学生でも安心してコンタクトが取れるのが利点です。
SNSやOB訪問アプリ
最近は Matcher などのOG・OB訪問アプリや、LinkedInを使う学生も増えています。SNSで先輩に直接コンタクトを取るケースも少なくありません。
おそらく、近年で一番メジャーなOBOGの探し方が、この「OBOG訪問アプリ・サービス」を使用することです。
ここでは特におすすめサービスを2つ紹介します。
Macher
Macherは登録者が多い&大学関係なく話を聞くことが可能です。そのため、幅広い学生さんにおすすめです!
「xxするので就活相談にのります」という形式でプランが用意されています。(ただこちら学生さんに何かを求めるといいうより、「就活相談にのるので、今ハマっていることを教えて欲しいです!」みたいな内容が多いです)
ビズリーチキャンパス
ビズリーチキャンパスは、同じ大学の先輩に話を聞くことが可能です。同じ大学繋がりということで、共通の話題も多いですし、信頼してお話することが可能です。
色々な業界の先輩がいるので、多様なお話を聞くことができます!
サークル・ゼミのつながり
身近な人脈を使うのも有効な手段です。同じゼミや研究室の先輩、部活やサークルのOB・OGにお願いすれば、共通の話題が多いため打ち解けやすく、ざっくばらんな本音を聞ける可能性が高まります。
非公式な紹介になるので、形式ばらないカジュアルな雰囲気で情報を得たいときにおすすめです。
OB OG訪問のための事前準備
OBOG訪問は、ただ会いに行くだけではもったいない時間になってしまうので事前準備が大切です。
そして、事前準備でOBOGに接する時のマナーも、同時にご紹介します。マナー違反をすると悪印象を与えてしまう・話をしてくれもらえなくなる可能性もあります。
アポイントを丁寧に撮る
最初のコンタクトは特に丁寧にしましょう。
最初の連絡はメールやSNSのメッセージが一般的です。ここでの第一印象が、その後のやりとり全体に響きます。文章は長くなくてもよいですが、
- 自己紹介(大学・学年・名前)
- 訪問の目的(就職活動の情報収集をしたい など)
- 希望日時(複数候補を出す)
は必ず入れておきたいところです。社会人は日々忙しいので「〇月〇日〜〇日の間で、午後でしたらいつでも可能です」といった配慮があると、返信率も高くなります。
事前に聞きたいことを整理する
せっかく先輩と会えるのに、その場で思いつきで質問してしまうと、表面的な話だけで終わりがちです。事前にノートやスマホにメモを作っておきましょう。
たとえば、
- 入社の決め手になったポイントは?
- 1日のスケジュールや働き方は?
- 学生時代にやっておいてよかったことは?
- 実際に働いてみて感じたギャップは?
こうした具体的な質問を用意しておくと、会話が広がりやすくなります。「なぜその質問をするのか」まで考えておくと、さらに相手の答えが深まります。
企業研究をしておく
最低限の企業情報を知ってから臨むことで、OBOG訪問は“雑談”から“深い情報収集”に変わります。
会社概要や業績、直近のニュースくらいは公式サイトで簡単にチェックできます。
例えば「最近新しい海外拠点を開設されたと知りましたが、実際に社員の立場でどう感じますか?」と聞けると、相手も「お、この学生は準備してきているな」と感じ、より具体的な話をしてくれることが多いです。
企業研究をしておく
意外と忘れがちなのが前日の連絡です。内容はシンプルで構いません。
「明日〇時に〇〇でお会いできることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。」
この一文を送るだけで、社会人としての礼儀をわきまえている印象になります。相手にとっても「本当に来るのかな?」という不安がなくなるので、訪問当日をスムーズに迎えられます。
OB OG訪問当日の流れ・注意ポイント
訪問当日は限られた時間で、できるだけ多くの学びを得る場にしましょう。
準備してきたことを活かしつつ、相手に失礼のないよう行動することで、会話がスムーズに進み、良い印象を残せます。気をつけるべきポイントをいくつかご紹介します!
時間に余裕をもって到着する
遅刻はもちろん厳禁ですが、ギリギリに着くのも慌ただしい印象を与えます。
対面で会う場合は、約束の10分前には現地に到着し、落ち着いてから訪問に臨むのがおすすめです。カフェやオフィスの近くで待機してから向かえば安心です。
オンラインの場合でも、5分前には入室準備を整えておきましょう。ネットワークの接続が悪くないかも確認するのがベストです。
第一印象を大切にする
初対面で一番に伝わるのは挨拶と身だしなみです。
清潔感のある服装を心がけ、挨拶ははっきりした声で「本日はお時間いただきありがとうございます」と一言添えてスタートしましょう。
(オンラインの時も、きちんと場にあった服をきましょう&背景の部屋も綺麗にしておきましょう)
話し方も「〜すか」など崩さないように気をつけましょう。
形式ばった敬語でなくてもかまいませんが、礼儀を意識した言葉づかいが好印象につながります。
最初の1〜2分がその後の印象を左右するので、特に第一印象をよくするように最大限努力しましょう!
会話は「聞く」姿勢を意識する
自分の疑問を解消するのが目的ですが、相手の話を引き出すことが大切です。自分のことを話しすぎると、せっかくの時間が自己紹介で終わってしまいます。
質問はシンプルに、相手の回答を引き出すことを優先しましょう。
うなずきや相づちを交えながら「それはどういうことですか?」と掘り下げて聞くと、相手も話しやすくなります。
メモを取りながら聞くと、真剣さが伝わり、自分の整理にも役立ちます。
相槌の「なるほど」には注意しましょう。
「なるほど…XXということなんですね!」というふうに、会話の接着剤とするならよいのですが、
「なるほど。」だけで止めてしまうと、「会話を流された」「ちゃんと聞いてない」と嫌な気分になります。
相手に配慮した時間の使い方をする
OBOG訪問は30分〜1時間程度が一般的です。盛り上がるとつい長引きそうになりますが、相手の時間を奪いすぎないよう注意が必要です。
終了予定の10分前になったら「そろそろお時間大丈夫ですか?」と声をかけると、相手も安心して話を続けてくれます。
時間を気にする姿勢そのもので、社会人としてのマナーをわかっている、という見え方をされます。
感謝の気持ちを伝える
話がひと通り終わったら「今日はありがとうございました」としっかり伝えましょう。
最後は「本日はありがとうございました」で締めましょう。
それだけでなく、「実際に働く方の声を聞いて、業界への理解が深まりました」「面接準備の参考になりました」と、学んだことを具体的に伝えると、相手も話した甲斐を感じてくれます。
好印象を残しておけば、後日相談に乗ってもらえる関係に発展することもあります。
OB OG訪問後にすべきこと
OBOG訪問は当日で終わりではなく、その後の振る舞いが信頼関係や情報の定着につながります。せっかく得たつながりを無駄にしないためにも、訪問後のアクションを整理しておきましょう。
お礼メールを送る
訪問から24時間以内に、短いお礼メールを送りましょう。内容は長文でなくても構いません。
「本日は貴重なお時間をありがとうございました」
「特に〇〇のお話が印象に残り、△△の準備に役立ちそうです」
といった具体的な感想を一文入れると気持ちが伝わります。
次のアクションに繋げる
訪問で聞いた内容を自分の言葉でまとめておくと、記憶に残りやすく、ESや面接で自然に活かせます。
ノートに「気づき」「学んだ点」「今後のアクション」を3つに分けて整理しておくと後から見返しやすいです。
また、聞いた内容を参考に企業研究を深めたり、他のOBOGにも会って比較したりすると理解が一層深まります。
単に“いい話を聞いた”で終わらせず、次の行動にどうつなげるかを考えましょう。
継続的な関係を築く
印象のよい訪問ができた場合、数か月後に進捗を報告するのもひとつの方法です。
たとえば「教えていただいた業界研究を進めた結果、この企業にエントリーしました」と連絡すれば、先輩も応援しやすくなります。
今後の選考でもお手伝いをしてくれることもありますし、就活を超えて相談できる“社会人の知り合い”になってくれる可能性もあります。
OB OG訪問の質問リスト
一連の流れがわかったところで、何をきくべきか?の参考に、よくある質問リストをご用意しました。
仕事内容・働き方について
- 1日のスケジュールはどんな流れですか?
- 入社して最初に任された仕事はどんなものでしたか?
- 普段やり取りする部署やお客さんはどんな人が多いですか?
- 忙しい時期と落ち着いている時期の違いは?
会社の雰囲気・カルチャーについて
- 社内の雰囲気を一言で表すとどういう感じですか?
- 上司や先輩との関係性はどんな距離感ですか?
- 若手でも挑戦できる環境はありますか?
- 他社と比べて「この会社らしい」と思う特徴は何ですか?
キャリア・就活のヒントについて
- なぜこの会社を選んだのですか?
- 学生時代にやっておいてよかったことはありますか?
- 就活で苦労したことや工夫したことは?
- 今振り返って「就活中の自分に伝えたいこと」は何ですか?
OB OG訪問で聞かないほうがいい質問リスト
OBOG訪問はリアルな話を聞ける場ですが、聞き方によっては「失礼」「配慮が足りない」と思われることもあります。ここでは注意したい質問をカテゴリごとにまとめました。
待遇・お金に踏み込みすぎる質問
- 給料っていくらくらいもらえますか?
- ボーナスはどのくらい出ますか?
- 残業代ってちゃんと出るんですか?
※公開情報や求人票で確認できる内容を直球で聞くのは避けた方が無難です。
一律NGというわけではなく、「ぶっちゃけた話もきいていいよ」という雰囲気だったら、聞いても大丈夫です!
選考に直結する質問
- 特別ルートで選考に呼んでもらえませんか?
- 面接で聞かれる質問を教えてください。
- エントリーシートを添削してくれませんか?
※初対面で“特典”を求めるのは好印象につながりません。アドバイスをもらう程度にとどめるのが安全です。
OB OG訪問で注意すべきこと
一連の流れがわかったところで、細々とした点での注意点を紹介します。
ここまで気をつかえたらあなたはOBOG訪問マスターです!
アポ取りの注意点
- 初回連絡は自己紹介+目的+候補日時(3つ)+所要時間(30〜45分)を一通り。
- 返信がないときは3営業日あけて一度だけ軽くリマインド。追いメールを連発しない。
- もしそれでもお返事がないときは一旦向こうからの連絡を待つ(急な出張・プライベートで不幸などでお返事できない可能性もあるので)
遅刻しそうになった時とリスケ
- 遅れそうなら到着見込み時刻を最初に伝える(「10分遅れます」より「○:○到着予定です」)。
- リスケはやむを得ない事情のみ。代替候補を自分から複数提示してサッと決め切る。
服装・持ち物
- 指定がなければシンプルで清潔感ある私服 or オフィスカジュアルで十分。
- 筆記用具/メモ帳/名刺代わりの簡単プロフィール(1枚)があると会話が進みやすい。
- 録音は事前許可が取れた場合のみ。
情報の扱い・守秘
- 聞いた話は個人名や固有名詞を外して自分のノートへ。
- SNSやブログでの発信は原則NG。どうしても引用したいなら事前に文面確認をお願いする。
- 録音・写真撮影は明示の許可があるときだけ。
紹介依頼・リファラルの距離感
- 初回で「他の方のご紹介を…」は控えめに。話が合って関係ができたあとに一言添える程度。
- 選考の依頼や評価のお願いを直接持ちかけない(リクルーター制度等は会社ごとにルールが異なるのと、がめつい印象を与えるため)
ハラスメントに対する注意
- プライベートや家族、政治・宗教など、相手が答えにくい話題に踏み込まない。
- 初対面・特に異性の人と個室で会わない。
- 相手からの態度で違和感があればその場で切り上げOK。「聞きたいことを聞けました。本日は貴重なお時間ありがとうございました」で終了して問題なし。
トラブル時の振る舞い
- 無断欠席は信用を失うので絶対にNG。やむを得ない体調不良でも開始前に必ず一報を入れる。
- ミス連絡をしてしまったら、言い訳より先にお詫び→改善策の順で。
まとめ
- OG・OB訪問は 大学3年の夏以降がベスト。早めに始めればさらに有利
- キャリアセンター、SNS、サークルなど様々な方法で探せる
- 事前準備をしっかりし、マナーを意識してお話する
- せっかくの縁を切らないように継続的に連絡を取り合う
就活のスタートダッシュを切るには、ネットでは得られないリアルな声を集めることが重要です。
「OG・OB訪問はちょっと緊張する…」という人も、まずは1件、軽い気持ちで動いてみましょう。その一歩が、未来のキャリアを大きく変えるかもしれません。
また、就活にまだ慣れていない、、という人は、こちらの記事をどうぞ!