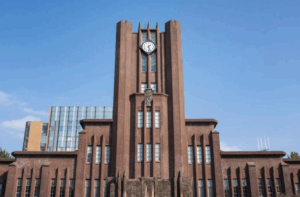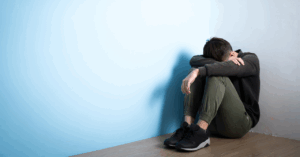こんにちは!優秀層向けインターンシップサービス「STURENT」運営事務局です。
今回は「コンサルティング業界」の業界研究記事です。
この記事を読めば、「コンサルティング業界に興味がある」「どんな選考スケジュールなの?」「ぶっちゃけ、難しいの?」という疑問もまるっと解消可能です!
元戦略コンサルタントの先輩の声も交えながら、コンサル就活のリアルをみてみましょう。
コンサルティングとは?
まずはコンサルティング業界の基本を抑えて行きましょう。
コンサルティングの基本的な役割
コンサルティングとは、企業や組織が抱える課題を解決し、成長や競争力強化をサポートする専門的なサービスです。といっても、経営戦略の立案から業務改善、新規事業の立ち上げ、人材マネジメント、IT導入まで、その領域は多岐にわたります。(コンサル業界内での分類は後述)
いずれの分類においても、クライアント自身が気づいていない問題点を見抜き、最適な解決策を提案・実行することがコンサルタントの重要な役割です。
企業がコンサルを必要とする理由って?
企業の中には、社長も、その道何十年のベテランもいる中で、なぜコンサルを必要とするのか?と疑問に思う方もいるでしょう。
企業は常に変化する市場環境の中で、新しい戦略や仕組みを求められます。
しかし、社内のリソースや知識だけでは十分に対応できない場合があります。そこで、外部の専門家であるコンサルタントに依頼することで、第三者視点からの客観的な分析や、他社事例に基づくノウハウを取り入れることができます。また、短期間で成果を出すための実行支援を受けられる点も、コンサルを活用する大きな理由です。
業界内の分類
コンサルティングには、戦略、業務、ITなど色々な種類があります。
そのため、よく調べないと「思っていたコンサルティングと全然違う」と思うことになります。
大まかな分類をご紹介します。
戦略コンサルティング
- 企業の経営戦略、新規事業立案、M&A戦略などをサポート。
- 経営層と直接やりとりするケースが多く、最も「ハイレベルな課題解決」を担う。
- 例:マッキンゼー、BCG、ベインなど。
総合コンサルティング(業務コンサルとも)
- 戦略立案から業務改善、IT導入まで幅広く対応。
- クライアントの課題を一貫して支援するのが特徴。
- 例:アクセンチュア、デロイト、PwC、KPMG、EYなど
ITコンサルティング
- ITシステム導入、DX推進、データ分析などに特化。
- 技術理解と経営視点を兼ね備える必要がある。
- 例:アクセンチュア(テクノロジー部門)、IBM、NTTデータなど。
人事・組織コンサルティング
- 組織改革、人材育成、人事制度設計などをサポート。
- 組織文化の変革や働き方改革などがテーマになる。
- 例:マーサー、アオンヒューイットなど。
財務・会計コンサルティング
- 財務戦略、M&A支援、企業価値評価などに特化。
- 公認会計士資格を持つ人材が多い。
- 例:BIG4の財務アドバイザリー部門。
他業界との違い
広告代理店やシンクタンクなども「企業を支援する仕事」として混同されやすいですが、コンサルティングはより「経営の根幹」に踏み込んで幅広く支援する点が特徴です。
広告代理店はマーケティング支援が中心であり、シンクタンクは調査や研究の比重が大きいのに対し、コンサルは「戦略立案から実行まで」を一貫して担うといったように、支援領域が広いというところに違いがあります。
(特に大手コンサルティングファームでは、戦略・業務・IT部門が連携して一貫した支援を実施可能。)
コンサルタントに求められるスキル
コンサルタントには、データをもとに結論を導く論理的思考力や、複雑な課題を整理する構造化力が求められます。また、クライアント企業の経営層と議論する場面も多いため、プレゼンテーション能力や説得力のあるコミュニケーション能力も不可欠です。
さらに、長時間労働やプレッシャーの大きい環境でも成果を出し続けるタフさも大切です。
これらのスキルは、コンサル業界に限らず他業界でも強力な武器になります。
特に戦略コンサル経験者は転職時、引くて数多となります。
終身雇用が前提ではなくなりつつある今、どんな道を選んでも自分に有利な選択をとれるようにと、学生からのコンサル人気も高まってきています。
コンサル業界の魅力と厳しさ
コンサル業界の魅力は、なんといっても抜群の成長環境が整っていることでしょう。
若いうちから大企業の経営課題に関わり、大きなインパクトを与える仕事ができます。
また、短期間で圧倒的に成長できる環境であり、他業界へキャリアチェンジしても高く評価されます。
一方で、成果主義の世界であるため、常に高いアウトプットを求められ、激務になりやすいという厳しさもあります。
やりがいとハードワークが表裏一体となった業界といえるでしょう。
コンサル業界の就活難易度って?
コンサルティング業界の就活難易度は、分類によって異なります。
戦略コンサルは最難関レベル
マッキンゼーやBCG、ベインといった戦略ファームは、就活全体でも最難関といわれる存在です。採用人数が少なく、ESからジョブまでのふるい落としが厳格。東大・京大・早慶トップ層でも容赦無く落ちるのが現実です。準備を徹底しないと太刀打ちできない領域です。
総合コンサルは間口が広いが競争率は高い
デロイトやアクセンチュア、PwCなどの総合ファームは採用人数が多いぶん、チャンスは広がっています。ただし応募者数も圧倒的に多く、倍率は依然として高めです。ES・Webテスト・GD・面接とステップが多いため、総合的に安定した力を出せる学生が評価されます。
IT・専門コンサルは対策次第で狙える
ITコンサルや人事・財務特化の専門ファームは、戦略や総合と比べると難易度は下がります。ただし、ITスキルや会計知識など専門性が求められる場面もあり、準備不足だと不利になることも。志望動機や業界理解がしっかりしているかどうかが合否を左右します。
どんな人が向いてる?
コンサル業界は「頭がいい人が集まる」「激務」というイメージが強いですが、実際に求められるのは単なる学歴やIQだけではありません。
というか、「めちゃくちゃ頭がいい」だけではコンサルタントは絶対に務まりません。
クライアント企業の課題を深く理解し、解決策を導き出すためには、以下のような特性を持つ人が向いているといえます。
論理的思考力が高い人
複雑な情報を整理し、筋道立てて結論を出せる人はコンサルタントとして不可欠な能力です。
まず一定この能力がない場合は、選考を通過すること自体難しいでしょう。
仮説を立てて正しく検証し、最短ルートで答えに近づく力は、コンサルタントとして必須の能力です。
コミュニケーション能力が高い人
経営層への提案や現場社員へのヒアリングなど、コンサルタントは人との対話が多い仕事です。
周りとうまくやっていける人・理解してもらえるプレゼン能力がある人が活躍します。
わかりやすく説明する力や、相手の意図をくみ取る力がある人は信頼を得やすく、間違いなく成果にもつながります。
粘り強く取り組める人
コンサルの現場では、短期間で膨大な情報を調査・分析する必要があります。
最近は以前ほどの長時間労働は少なくなってきているものの、深夜まで作業が続くこともあります。
そして、「答えが出ない問題」に対して答えを見つけていく作業がほとんどなので、常にプレッシャーがかかります。
そんな中でも粘り強くやり抜ける人は高く評価されます。
学び続ける意欲がある人
クライアントの業界は多種多様で、プロジェクトごとに新しい知識を吸収しなければなりません。
そうでなければ、ただの素人のなんちゃってコンサルになってしまうからです。
常に学び続け、新しい情報をインプットして自分の武器にできる人は、長く活躍できます。
成長意欲と向上心が強い人
コンサルは20代から経営レベルの課題に関わることができる環境です。その分、自己成長のスピードも早いですが、主体的に成長を求める姿勢がないと厳しい業界でもあります。「もっとできるようになりたい」という強い意欲を持つ人は向いています。
コンサルティングファームの選考って?
エントリーシート(ES)
コンサル業界の選考では、ESはあまり重要視されません。というのも、一定の地頭のよさを図るために「学歴」を重視しているからです。
東大京大であればESは基本通過します。(とはいえ、面接時はこのESを見て会話されるため、手を抜いてはいけません。)
ただ近年は、以前よりも広い学歴の方に門戸が開かれるようになっているので、学歴に少し自信がないという方は、「論理性」と「再現性のある成果経験」が示せているか確認しましょう。
単なる体験談ではなく、「課題→自分の行動→結果」という因果関係が整理されているかが見られます。
筆記試験・Webテスト
面接の前のふるいとして機能するのが、学歴とWEBテストです。
英語力や論理力を測るテストに加えて、図表読解や数的処理等のWEBテストが採用されます。企業によって、出題される問題は多様ですが、たいていどんなテストがでるかの情報は出回っているので、気になった場合は事前に調べてから試験に臨みましょう。
高学歴であってもWEBテストで落ちるというケースは珍しくないため、最大限の努力をしましょう。
グループディスカッション(GD)
グルディスは、数人の学生がひとつのテーマについて議論し、制限時間内に結論をまとめる選考形式です。テーマは「新しい飲料ブランドを広めるには?」といったマーケ寄りのものから、「地方の過疎問題を解決するには?」のような社会課題まで幅広く出題されます。
評価されるのは“リーダーシップを発揮できるか”だけではありません。論点を整理する力、他人の意見をうまく引き出す姿勢、議論を前に進める貢献度など、多角的に見られます。声が大きい人だけが評価されるわけではなく、議論を冷静に構造化したり、抜けている視点を補ったりする役割も重視されます。
コンサルグルディスでは、がんがん意見が飛び交うので怖いですが、「話すのが苦手」という人であっても、議論の方向性を変えるような一言を投げたり、意見をまとめたりという役割をになったりすることで評価されます。
フェルミ推定・ケース面接
コンサル選考の代名詞ともいえるのがフェルミ・ケース面接です。「日本の電柱の数を推定せよ」「ある飲食チェーンが売上を伸ばすには?」といったテーマをもとに、その場で論理的に考えを組み立て、面接官と議論を重ねます。
正解はひとつではなく、仮説を立てて数字を使いながら話を展開できるかが重要です。緊張する場面ですが、面接官は“答え”よりも“考え方の筋道”を見ています。
フィット面接(人物面接)
ケース面接を通過した後か、複数回のフェルミ・ケース面接の間に行われることがあるのが人物面接。
最終的には「一緒に働きたいか」が問われます。どんなに論理的で優秀でも、チームで協力できなければプロジェクトは成り立ちません。過去の経験を通じて「困難をどう乗り越えたか」「周囲をどう巻き込んだか」を問われることが多いです。ここでの受け答えが、内定の決め手になることもあります。
ジョブ(戦略ファーム特有)
戦略ファームの選考で最大の山場となるのが「ジョブ」です。数日間にわたり、何人かのメンバーとチームで実際のケースに近い課題に取り組みます。形式はインターンと同じですが、採用に直結する大事なフローです。
選考の中でも、一番総合力を試されハードな試練となり、最後の山場となります。
インターン選考と本選考の関係
多くのファームでは、サマーインターンやウィンターインターンを「事実上の選考ルート」として位置づけています。
特に戦略系コンサルでは、インターンが選考直結になっていることがほとんどであり、事実上の本選考とも言えるため、戦略コンサル希望者はインターンに参加しましょう。
ただ、逆にインターンで不合格になったり、インターン中で活躍できなかったりすると、その後の選考に影響を与えるため、インターンは“腕試し”ではなく“本番の一部”と考えるべきです。
コンサルティングファームの選考スケジュール
コンサルティングファームの先行スケジュールは、戦略系と非戦略系で大きく異なります。
それぞれのスケジュールをご紹介します。
戦略系ファーム
インターン参加が肝!! 多くの採用がインターン経由のため、本気の人はインターンに参加しましょう。
ただ、インターン=本選考と同じ扱いですので、本気で挑みましょう。
3年夏〜秋(6〜9月)
- サマーインターン(=ジョブ)の選考開始
- ES → Webテスト → ケース面接(複数回)
- 数日間のジョブに参加
- 評価が高ければ早期内定 or 冬のジョブ案内
3年冬(12〜2月)
- ウィンターインターン(ジョブ)実施
- サマーで落ちた学生のリベンジ機会
- 優秀者はこの段階で内定直結
4年春以降(3月〜)
- 本選考(ただし大半の内定はジョブ経由で決まっている)
- ケース面接中心、最終はパートナー面接
その他(総合・IT・人事など)のファーム
総合・ITは「インターン=本番」ではなく「就活準備の一部」色が強いです。ただし参加者は早期に情報を得やすく、有利に動ける場合があります。
出遅れてしまったとしても、一般の就活スケジュールとほぼ同じに動いて問題ありません。
3年夏(6〜9月)
- サマーインターン選考
- 内容は会社理解+ワーク(ジョブほどシビアではない)
- 優遇ルートにつながる場合もある
3年秋〜冬(10〜2月)
- オータム・ウィンターインターン開催(任意参加)
- 本格的な選考直結は少なめ。社員交流や業務体験が中心。
3年冬〜4年春(2〜4月)
- 本選考スタート
- ES → Webテスト → 面接(複数回)
- ケース面接はあるが、戦略より難度は低め
- 内定は4年春〜夏に集中
まとめ
コンサル業界は「論理的に考える力」「新しいことを学び続ける姿勢」「粘り強さ」が求められる世界です。仕事内容は戦略立案から業務改善、IT導入まで幅広く、戦略ファームか総合ファームかによって働き方や選考の流れも大きく変わります。
特に戦略コンサルでは、インターン型の本選考プロセスが最大の勝負どころ。ここで評価されるかどうかが内定に直結します。一方で総合・IT系のファームは、インターンは情報収集や社員理解の色合いが強く、本選考でじっくり評価される傾向があります。
どのファームを目指すにせよ、共通して大切なのは「準備」と「自己理解」です。ESや面接で論理性を示すだけでなく、自分がなぜコンサルに挑戦したいのか、どんなキャリアを築きたいのかを言葉にできる学生は強いです。
もしあなたが「大きな課題に挑戦したい」「短期間で圧倒的に成長したい」と思うなら、コンサル業界は間違いなく挑戦する価値があります。激務と引き換えに得られる経験は、将来のキャリアに大きな財産となるでしょう。
そしてもし新卒で戦略コンサルタントに行けなくても、第二新卒で再挑戦することも可能です。
↓実際に2卒で戦コンに行った先輩の体験談はこちら。